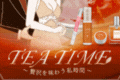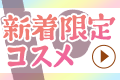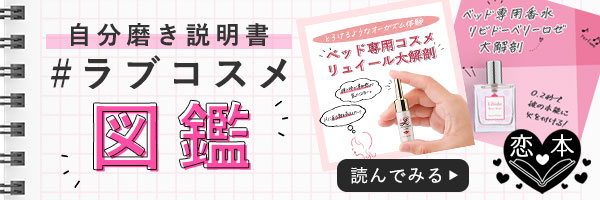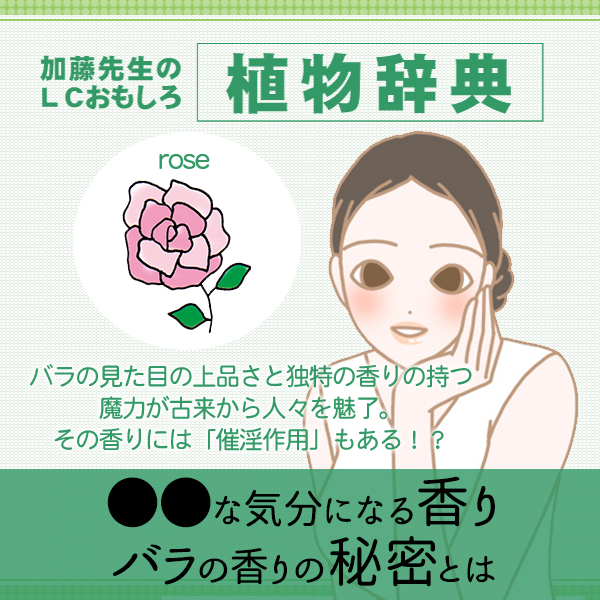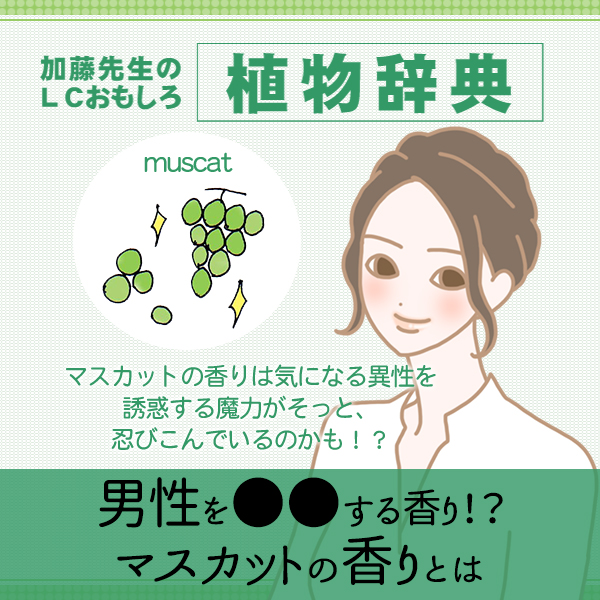カカオの違いとは?

チョコレートの原料でカカオ豆由来のものは「カカオマス」と「カカオバター」です。 カカオマスとは、カカオ豆の皮と胚芽を取り除いてすりつぶし、固形状に固めたもの。 カカオバターとは、カカオ豆に5割程度含まれている脂肪分。 蛇足ですが、ココアに用いる「ココアパウダー」は、カカオマスをある程度脱脂してから粉末にしたもので、330粒のカカオ豆からは1kgのココアパウダーが取れるそうです。
つまり、もともとは飲み物だったチョコレートを飲みやすくしたのがココアで、固めたのがチョコレートだという関係からすれば、チョコレートもココアも親戚というより兄弟みたいなもの。
それゆえ、機能の部分でもほぼ同じといってもよいでしょう。 注目すべき成分には「カカオポリフェノール」「テオブロミン」などがあります。
女性の大敵にも!?
まずは「カカオポリフェノール」。渋みこそがポリフェノールそのもので、ひとことでいえば抗酸化物質。体内の活性酸素を抑える働きが知られています。有名な赤ワインのポリフェノールよりも含有量は多いようです。
研究により分かったのは、「動脈硬化を防ぐ働き」、細胞のDNAの突然変異を抑制する「ガン予防」の可能性、「ストレスに対する抵抗力を高める働き」、活性酸素の過剰な働きを抑えることによる「アレルギーを予防する働き」などがあることです。
次に「テオブロミン」。 テオブロミンが含まれた形である複合体であればガラナにも含まれていますが、単独ではカカオにしか含まれていない成分。中枢神経を刺激して末梢神経の活力を高めてストレスを防ぐ働きがあります。
また、毛細血管を広げる働きもあり、血流をよくしたり、血圧を安定させたりする働きがあります。当然、女性の大敵である冷え症に対しても有効に働きます。 カカオには胃潰瘍などと密接な関係を持つ「ピロリ菌」が増殖するのを抑える働きが知られていますが、テオブロミンがストレスを抑えることで、胃潰瘍の治癒を早める可能性も指摘されています。
チョコレートに癒されて…

また、こんな面白いデータもあります。 ラットで普通のエサを食べさせた群と、2割をチョコレートに置き換えた群とを比較したところ、カロリーが同じな場合、体重の差がみられなかったというもの。
つまり、"チョコレートで太る"というのは迷信だということ。 しかし、残念ながら、ダイエット効果があるとまではいえませんが。 最後に、チョコレートの香りについて。
海外ではチョコレートセラピーという、チョコレートを用いたパックやクリームのエステがあり、最近は日本にも上陸しています。 チョコレートの香りが集中力や注意力、記憶力を高めることは脳波試験などから確認されています。 これだけにとどまらず、チョコレートの香りがドーパミンやβ-エンドルフィンのような脳内物質の物質の分泌を促進することで、「癒し」ともいうべきメンタル的な作用を期待したものと思われます。
薬剤師。1969年東京薬科大学卒業。
1992年伝説のクイズ番組『カルトQ』(フジテレビ系)で最高得点を記録し優勝。これまで、調剤薬局運営や薬剤師ライターとして多数の健康雑誌に連載を持つなど活躍。