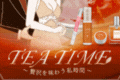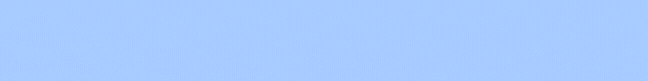夕暮れ近い駅ビル。親友の裕子と2カ月ぶりに会い、朝からショッピングをおしゃべりの同時進行が続いている。
「あ、これ、可愛い!」裕子の声に振り返ると、彼女の前にはランジェリーショップのイチオシ商品。「ほんとだ、可愛いね~。綺麗なレース!」「じゃ、ユカリ、色違いで一緒に買おうよ。ユカリは、ピンクだね~」
「うんうん!」とほとんど勢いで買ったレースの下着だけれど、いざ自分の物になると、ウキウキが1秒ごとに増していく。帰りの電車の中では、バッグを抱える手がくすぐったくなるほどだった。
その夜のバスタイムは、遊園地にいる幼い女の子のような気分になった。たっぷりとフワフワに膨らませた泡で全身を洗い、ヘアパックも丁寧に施し、のんびりとバスタブに浸かる。
さらに、お風呂上りには、ちょっと贅沢なボディミルクを全身に。しっとりツヤツヤした、ぷるんとお皿に揺れるプリンのような肌が鏡に映って、満足する。


「やっぱり、ちょっとだけ…」迷っていたけれど、やはり、買ったばかりのレースの下着をつけてみた。試着室でつけたときよりも、お風呂上りの艶に包まれた肌に、それは何倍も輝いて見えた。
親友とのショッピングもおしゃべりも、自分の下着姿も、すべてがアップテンポのメロディーの中に織り込まれていくような気分で、眠りにつく。
そのときには、想像もしていなかった。 あんなにハッピーに輝いていたピンク色のレースが、くすんで見えるときが来るなんて…。

「なんか今日、ユカリ、いい匂いする」食事の後、ホテルの部屋に入るなり、恋人の涼太は私をベッドに押し倒した。そのまま、カットソーをまくり上げ、胸に顔をうずめる。
「あれ?新しい?」涼太が、買ったばかりのブラに気づく。「うん、こないだ裕子と会ったときに買ったの」「いいね。色っぽいレース」そう言ってブラ上からキスをして、レースから溢れる柔らかな丘に吸い付いた。
「あぁ…」思わず息を漏らす私に、「ちゃんと見せて」と涼太はカットソーを脱がせ、ピンクのレースをまとっただけの上半身に視線を這わせる。
「うん、すごくよく似合ってる。可愛いよ、ユカリ」もう一度、唇とブラにキスをすると、背中に回した手で器用にホックを外して、レースに隠れていた部分をあらわにし、そこを改めて隠すように胸に顔を寄せ、その先端をコロコロと舌で転がした。
「あぁぁ…ん…」息が熱くなる私の目を、涼太は意地悪な視線で見つめる。「ここ、ユカリ、好きだよね」と言いながら胸の先端をそっと甘噛みする彼の頭を、同じ甘さで撫でた。
涼太は、私の胸を唾液で濡らしながら、スカートに手をかけ、スルリと脱がせる。「こっちも、見せて」脱がせたスカートに隠れていた下着に触れてから、彼は上体を起こし、ベッドに横たわる私を見下ろした。
「下も、可愛いね」と言うと、彼は私を四つん這いにさせて、「後ろからも、いい」とウエストからヒップ、太ももの裏をそっと撫でる。下着の上からそっとヒップにキスをすると、そのまま背骨に沿って首まで舌を這いあがらせた。
「シャワー…」私が小さく言うと、涼太も「そうだね。まずはお風呂に入ろうか」とバスルームへと向かった。
(何もおかしくない。何もおかしくないけど…)バスタブにお湯が落ち始める音を聞きながら、私は、ほんの少しの違和感を覚えていた。ブラを外して、スカートを脱がせるところまでは、涼太、あんなに興奮していたのに…。

急にテンションが変わったような…。(もしかして、私、におってるの…?)ベッドの上にひとりで座って、レースの下着に手を当てる。輝きもときめきも消え去った、沈んだピンク色の下着に。

「これ、どうかな?」裕子が、スマホをこちらに向ける。
もしかして自分のデリケートゾーンがにおっているのではないかなんて、できれば誰にも話したくなかった。けれど、その疑惑をひとりで抱え続けると、不安の波だけが大きくなっていく。
私は、思い切って裕子に打ち明けた。すると彼女は、早速自分のスマホを取り出し、あるサイトを見せてくれた。「実はね、私もちょっと気になってたんだ、同じこと。それで、ちょうどいろいろリサーチしてたんだよね」
裕子の言葉に、私は、沼の底から救い出されたような気分になる。「そうだったの?」驚きと同時に、私は、思わず裕子の手を握っていた。その手に握られたスマホの画面にあるのは、デリケートゾーンのパックらしい。
「パック?」「うん。植物由来の成分を使ってるから、デリケートなところに使っても優しそうだよ」「へぇ…そうなの?」
「ふたりともが、半信半疑で。それでも、ふたりともが不安とモヤモヤを消し去りたくて。 私たちは、下着を買ったときとはまた違う勢いで、そのパックを購入した。

数日後。注文したパックが届いてから、私は、毎日欠かさずにお風呂でケアをした。 最初は、においが気になるという理由だったけれど、使ってみるとスッキリとした感覚が心地いい。それに、キュッと引き締まるような気がする。まるで、毎日少しずつ変身しているような…。
それを感じてから、私は、デリケートゾーンだけでなく、ほかの部分にもそれまで以上に細やかに気を遣うようになった。肌や髪のケア、爪の手入れ、食事の内容や食べ方も。
涼太とのベッドタイムのために始めたデリケートゾーンのケアだったけれど、それだけじゃない。私、自分の体と、女性としての自分すべてと、こんなにちゃんと向き合っている。
それって、実は、すごく大切なことだったのではないか。そう気づくと、自分の体がとても愛おしくなった。

デリケートゾーンのパック「ジャムウ・デリケートパック」を使い始めてから、そろそろ1ヵ月が経つ。今日は、涼太の誕生日だ。
この1ヵ月の間、何度かデートをした。けれど、オーラルセックスは、さり気なく避けていた。パックをしていて「多分大丈夫だろうな」と思っていたけれど、におっているのかもしれないという不安が消えなくて…。
「ねぇ、ユカリ」誕生日ということで、普段よりもちょっと贅沢なレストランで食事をしていると、涼太が私の耳元で名前を呼ぶ。反射的に顔を上げると、彼は「お願いがある」と意味深な笑みを浮かべた。
「俺が、本当は舐めるの大好きなの、知ってるでしょ?今夜は、誕生日プレゼントに、いっぱい舐めさせて」さらに私の耳に口を近づけると、彼はそう囁いた。驚いた顔を、私は、彼に向けたと思う
そして、ホテルに入る頃には、その驚きの上に、"におっているのかも"という不安の膜が広がっていただろう。シャワーを浴びてベッドに並ぶと、涼太は「舐めていい?」ともう一度視線を合わせた。
私は、何も答えられない。イエスともノーとも言えないままに、彼に抱きついて、口づけた。涼太は、優しく舌を絡ませて、「大好きだよ、ユカリ」と熱い声を吐くと、少しずつ、舌を移動させる。

唇から、首へ。首から、肩へ。肩から、胸へ…。ウエストをすぎてしばらくすると、私は、無意識に脚に力が入る。その2本の緊張をそっと広げて、涼太は脚の間に顔をうずめた。
「大丈夫。心配しているようなことは、何もないよ」私の体のあちこちを撫でる彼の指からも、優しい声が馴染んでくる。
「舐めたい」興奮の混じった息を吐くと、彼は、その口の中に私のクリトリスを含んだ。 口の熱さに私の体がなじみ、彼の舌のざらつきが私の突起を少しずつ硬くするのが分かった。
「あぁぁ…」においのことが、少しも気にならなかったと言ったら、嘘になる。けれど、自分の唾液と私の愛液をじゅるじゅると吸いながら「おいしい」と息を荒くする彼に、私は次第に飲み込まれていった。
「あぁぁ…いい…きもちいい…涼太…」いっそう熱を増す彼の舌に、私のカラダは溶かされていった。「よかった。俺も…こんなにおいしいの、はじめて」泉の中に硬くとがらせた舌を沈み込ませながら、彼はさらに息を熱くする。
「ねぇ…涼太…ほしい」全身から力が抜けるほどに舐められて、私は、初めて、彼にそうお願いした。「ジャムウ・デリケートパック」で秘密の変身をしたつもりだったけれど、もっともっと大きな変身が、幸福な快感の向こう側に待っていた。
本当に溶けてしまうのではないかというほどに泉に舌を這わされ、体のすべてがしびれるような感覚の中で迎え入れる彼自身は、格別に愛おしい。
彼をしっかりとつかまえようとする泉の躍動と、全身の細胞から湧き上がってくる愛おしさを噛みしめながら、私は、それまでで一番強い力で、愛する恋人を抱きしめた。
~第二話・完~

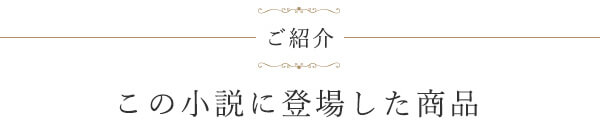
肌の細胞すべてに、体の動きすべてに、心が宿る。 心が宿った肌を合わせれば、幸せが身に沁みる。 愛する幸せ、愛される幸せ、女性としての幸せ、人として生きる幸せ。
いろんな幸せが宿るセックスが、日々、たくさん生まれますように。 …そう祈りながら、小説の執筆をしております。
⇒【はづき】さんの官能小説はこちら
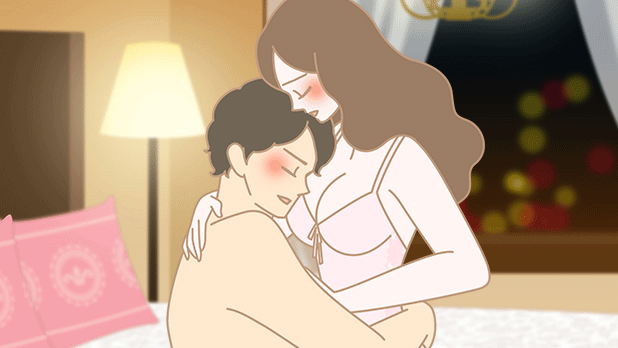
この物語の元になった体験談はこちら!
(しゅーさん/22歳/会社員)。エッチにも集中ができ、オーラル好きの彼に「こんなに美味しいのは初めて!」という嬉しい言葉も頂きました。どうやら無味無臭のようで、とても長い時間舐められ…