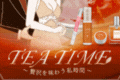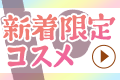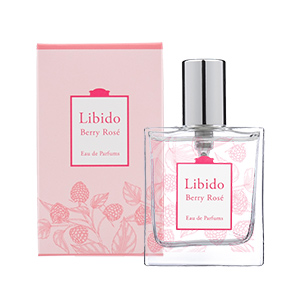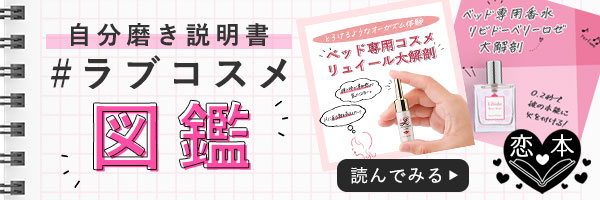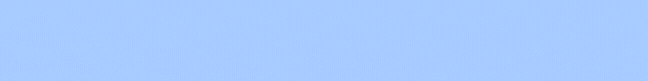江戸時代、平均初婚年齢が最も高かったのは「販売業」
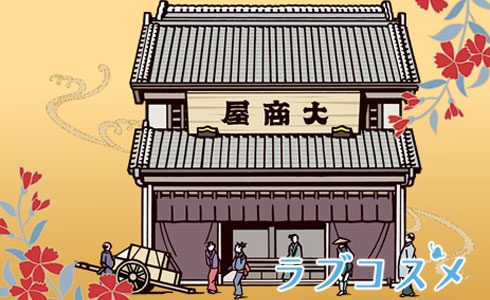
江戸時代の男性で、平均初婚年齢が一番高かった職業は…というと、それは販売業でした。それも現代でいう、ハイクラスな販売業の場合なんですね。彼らは少年時代から使用人として豪商の店に住み込みの仕事を続けていました。だんだん出世していって最後に辿り着くのが、現代でいう「支配人」に相当する番頭のポストなのでした。
ところが、この番頭のポストに就けるのは早くて三十代はじめ。それまでは一人前の男性ではないとされ、結婚の自由すらも与えられないことも多かったのです。豪商の店に勤める番頭さんは高給取りですし、社会的なステイタスも高いわけですが、江戸時代の彼らの平均初婚年齢は、現代日本男性を上回る三十歳以降だったことになりますね…。
しかし、平均寿命から考えると、三十代で男性が結婚した場合、残り寿命が下手すれば十年もないわけです。江戸時代には平均寿命も上昇したとされますが、男女ともに三十歳代~四十歳代前半くらいなんですね。乳幼児が亡くなる率が高かったという理由を加味しても、かなりの晩婚だといえるでしょう。江戸時代の女性が(離別・死別をとわず)シングルになった後、何度も結婚した…という理由のひとつがわかる気がします。
ライフスタイルの多様化で出現した『恋愛しない派』

初婚年齢についての正確な統計が日本で取られはじめたのは明治後期です。国立社会保障・人口問題研究所のウェブサイトによると、1910(明治43)年の平均初婚年齢は夫27.0歳、妻23.0歳でした。女性は江戸時代とかわらず、比較的若くして結婚するものと考えられていたのだなぁ…という印象はありますね。
現代日本では、女性も男性と同じように、勉強を終えたあとは社会に出て職業を持ち、働くのが普通というように時代背景が変化しています。たしかにお役人や政治家の先生がいうように、これらの要因が女性の初婚年齢を上げている原因なのでしょう。
恋愛結婚が主流となっている現代日本ですが、その恋愛自体を、難なく普通にこなせる層とそうとはいえない層に二分されてしまっている印象があります。恋愛しない派については、ライフスタイルや娯楽が多様化したがゆえに、恋愛以外にもたくさん楽しみが生まれたから…という説明がされることも増えました。時間の使い方の選択肢が「細分化」されてしまい、あれもこれもとついつい欲張りになってしまううちに、恋愛するチャンスを失ってしまう場合もあるのかもしれませんね。これは日本の歴史の中でも、現代特有の現象のように思いますが。
結婚にはやはり「決断」が必要!

理想なのは、「いつの日か素敵な男性と出逢う」式の展開なのですが、残念ながら、仕事が忙しく、出逢いはあっても恋愛にはならないとか、ラッキーなことに「素敵な男性」と出逢い、お付き合いしたところで、お互いに求める条件が合わず、結婚には到らないまま…なんてケースが多々ある気がしませんか?あるいは、「そのうち本命が見つかるだろう」と楽観、恋愛については超奔放、なのに結婚については超保守的に考える人も多くなってきているのかもしれませんね。
歴史的に考えれば、現代日本の平均初婚年齢はさほど高すぎるというわけでもないのです。平均寿命も延びましたし。それでも女性の結婚年齢が比較的上昇しているのが、決断できない女性の増加と関係しているとするなら、そしてそれについてのアドバイス的なものをするなら、「結婚して幸せになりたい!」というだけでなく、「この人が大好きだから、この人のためにするどんな苦労でも我慢できる!」と思えるよう、意識を変えられるといいのかもしれませんね。

作家・歴史エッセイスト。古今東西の恋愛史や芸術・文化全般などについての執筆活動を続けている。
最近の出版物としては、原案・監修を務める『ラ・マキユーズ ヴェルサイユの化粧師』(KADOKAWA)のコミック第1巻が発売中。『 本当は怖い世界史 』シリーズ最新刊の 『愛と欲望の世界史』(三笠書房)も好評発売中。
堀江宏樹さんTwitter⇒https://twitter.com/horiehiroki
撮影:竹内摩耶