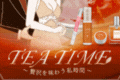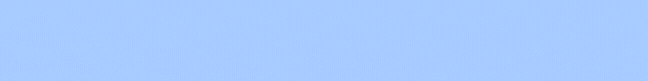「私、紗季先生みたいな40代になりたいんです」
レッスン前、スタジオにモップをかけていたら、優絵と彩芽がやってきた。
「この間、レッスンあとに出版社の方にインタビューされて。私達、そういう風にこたえちゃいました」
伊沢が、スタジオ前で待ち伏せしたのだろうか。やはり私よりも若い生徒さんがねらいだったとか。
「出版社の方、紗季先生のことずっと待っていましたよ」
疑心暗鬼になっていたら、見透かすように優枝が言った。
「そうそう。私、紗季先生の彼氏かと思ったもん」
モップを手にしたまま、うつむいた。私ったら、若さに嫉妬している。

「……本当に、私みたいな40代になりたいの?」
離婚後に起業して、ひとりでも大丈夫だと信じてきた。40代も後半になったら、男なんか自然に必要なくなると思っていた。
でもいざ好意をよせられると、すぐに揺らいでしまう。大きな身体やあたたかい皮膚に、まるごと守ってもらいたいと切望してしまう。
「40代って、けっこう情けないわよ」
自虐的に笑ってみた。すると優絵と彩芽は、
「30代だって大変です!」
口々に言ったのだ。だからこそ、今、努力して後悔しない40代を迎えたいのだと。
「紗季先生。これを見てください」
『ウーマンズライフ』に隣接するカフェで、伊沢が差し出したのはアンケート用紙だった。
「30代、40代でセックスレスの女性が多いかと思えば、50代、60代でもセックスをしている女性、したい女性はたくさんいるんです」
驚くことに、70代や80代でも性生活を謳歌していた。確率は少ないとはいえ、女というものを閉じ込めることなく解放している。
「伊沢さん。ひとりの男性として、こういう女性をどう思う?その、年配になってもセックスしたいと願う女性のこと」
正直にこたえて、と私は念を押した。
「僕は、すばらしいと思います。日本人男性は若い女性に傾倒しがちだけど、年を重ねた女性の素直な欲望を知ることによって、男性側も変わっていけばいいと思うんです」
「伊沢さん、私……」
実は、数ヶ月前から取り入れたいプログラムというか、グッズがあった。インナーボールやオイルなど、いわゆるセルフで女性器を鍛えたりケアするアイテムだ。
本格的な更年期を迎えれば膣が委縮する可能性もあるし、予防のためにもケアを習慣づけるべきなのではないか。
女性器のお手入れに抵抗感がある女性は多いだろう。でも、男性だって女性器は謎なのだ。まず女性側が理解を深めなければならない。
それにパートナーがいる、いないに関わらず、自分の身体をまるごと慈しむことで、女性はみんな、内面から輝くはずだ。

「紗季先生のように独立して、しかも内面から輝く女性に憧れる若い世代は多いんです」
……いつだったか、伊沢が私に言った。私は、女性のためにと謳った教室をひらいている。そんな私が実行に移さなくてどうするのだ。ヨガやハーブだけではなく、インナーボールやオイルなども、ここからポピュラーにしていけばいい。
「伊沢さん。あの……、私の考えを聞いてもらえますか」
顔から火が出そうになりながら、言葉を選んで伊沢に伝えた。伊沢は興奮したように身を乗り出し、
「そうです、僕もそういう本を紗季先生と作りたいんです」
私を、正面から見つめた。
「でも私」
プチ更年期の上に長年セックスしていない。こんな私が先導する形でいいのだろうか。
「でも、何ですか、紗季先生」
「私……」
いっそのこと白状してしまえばいい。延々と気を持たせるより、私自身もけじめがつく。ここであの告白がなかったことになっても、傷は浅くてすむ。
「私こそが、ご無沙汰なんです。もう10年以上も。笑っちゃうでしょう。『ウーマンズライフ』なんて主宰しているくせに、本当は身も心も不調。えらそうなこと言っているけど、自信なんかないんです」
笑って、何でもない風をよそおった。ハーブティーを飲もうとしても、うまくいかない。指がふるえているのだ。
だからきっと、本を書く資格はない。立ち上がろうとした私の手を、伊沢が握りしめた。
「そういうところが好きなんです。きっとたくさん、悩んできたんでしょう?でも女性のために奮闘している」
「離してください」
私から、手を振り払うことができない。一度別の熱を感じてしまったら、もうひとりでいたくなくなってしまう。
「……離してください」
伊沢は、まったく離そうとしない。それどころか、いっそう力を込めてくる。
「離したくないんです」
大胆に言いつつ、次第に伊沢の手が汗ばんできた。正直な人だ。
もがきながら、手探りで生きてきた。私の経験が、様々な女性の励みになるだろうか。
セカンドバージンからのセックスへの道。私が自分をさらけ出すことで、前向きな女性が増えていくのなら。
勇気を出しても、いいかもしれない。

「伊沢さん。私を、助けてくれますか」
私を、託していいですか。伊沢の手を握り返して、私は言った。
年齢や立場、人間関係や容姿など、女性は各々の事情を隠し、今日も健気に過ごしている。胸の内をほんの少しでも明かすことができたら、もっと晴れやかに笑えるかもしれない。
性的なコンプレックスは根深いけれど、手を差し伸べてくれる人は、必ずいる。男性に限定せず、女友達や、たとえば、そう、私のような。
私は同じ女性として、そんな架け橋になりたい。
「伊沢さん。女性は、いくつになっても輝けますよね」
伊沢が何度も何度も頷く。
「もちろんです」
よかった、と安堵しつつ、私も泣き笑いの顔になっているのだ。
埼玉県出身。元少女小説家、小説家。2013年新潮社『R-18文学賞』読者賞受賞。
『主婦病』『幸福なハダカ』『私の裸』新潮社より刊行。他、著書多数。cakesにてエッセイ連載中。
『アラフィフ作家の迷走性活』。