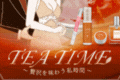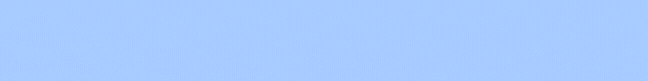『ウーマンズライフ』に通っているのは、自分のためではない。男のためだ。
ヨガは身体をやわらかくするから、どんな体位だってこなせるし、主宰者の安永紗季先生は骨盤底筋に特化したプログラムも組んでくれる。膣を鍛えれば、男の人に飽きられることはない。きっと。

シャワーを浴びるなり、貴也はすぐさまベッドで大の字になった。私も素早くシャワーを浴び、貴也の身体に覆いかぶさる。
体重をかけないよう、ていねいに愛撫していくのだ。
「気持ちいい?」
私の問いかけに、貴也の皮膚が熱でこたえる。ややあって、貴也が私を組み敷いた。
「彩芽って便利だよな。離したくない」
離したくない。女が一番よろこびそうな言葉だけど、矛先は私そのものではないことを、私はうすうす気づいていた。
ラブホテルで別れ、ひとり家路につくまでの時間が嫌いだ。
身体に残った男の感触が、中学三年生で初めてできた彼を思い出させる。
家庭教師の大学生で、真面目でやさしかった。
高校受験が終了した日にセックスをして、直後にフラれた。
私にとってのたった1回は、彼にとって試食品程度だったのだ。あとから、二股をかけられていたと知った。
自宅最寄り駅に降りると、LINEが届いていた。敦司だ。明日の夜会える旨返信し、夜空を見上げる。するとまた着信が鳴った。
『彩芽さん。月が綺麗だね』
勇真だった。こういう場合、「うん、綺麗」って返せばいいのだろうか。男とのSNSなんて、セックスの約束事だけで終始していたから、私にはわからない。
「それで、既読スルーのままにしたの?」
『ウーマンズライフ』に隣接したカフェで、レッスン後にお茶をしていた。首を傾げた優絵に、私は、
「だって、何てこたえればいいの」
「綺麗、って返せばいいのよ」
優絵がくすぐったげに笑う。最近優絵は、とてもきれいになった。
テーブルに置いたスマートフォンが光る。敦司だった。
「私そろそろ行かなきゃ。デートなの」
席を立つ私に、優絵が言った。
「デート?でも彩芽、なんかつらそうだよ」
「つらくなんかないけど」
「あ、ごめん。少し疲れているように見えたの」
「……ううん、私こそごめん。じゃ、行くね」
優絵に腹が立ったのは、図星だったからだ。デートだというのに私は、ラブホテルで過ごすのが義務のように感じている。
「気持ちいい?」
敦司は着衣のままするのが好きだ。私はベッドに横たわりたいのを我慢して、立ったまま中途半端に服を脱がせる。
「彩芽って、実用的だよな」
勝手に果てたと思ったら、私の頭を撫でてバスルームに消えた。便利。実用的。だから、離したくない。そんなのは違うって、わかっている。
素早く身支度を整えて、ラブホテルを後にした。夜空を見上げたら、月がふやけた。私は、泣いていた。今さら、と思いつつ、勇真にLINEをする。
『月が綺麗』
たくさんの男がいれば、大丈夫だと信じていた。かつて私を傷つけた男に、復讐する意味もあった。
『彩芽さん。明日、ごはんでも食べよう』
OKの絵文字を返信して、涙を拭う。ごはんだって。子供みたいだ。

翌日の夜、久しぶりに会った勇真ははしゃいでいた。何が食べたい?と街をうろつきながらしきりに聞いてくる。
「でも、時間的に中途半端じゃない?」
ホテルに直行した方が手っ取り早い、という意味だった。
勇真は私を正面から見据えて、
「あ、こういう時は洒落た店を男が予約しておくべきなのか。ごめん、俺、そういうのわかんなくて」
頭をかいたのだ。なんだか拍子抜けしてしまう。
「本当にごはん食べるつもりだったの?」
私がたずねると、犬みたいに頷く。
「いいわ。コンビニで買って、ホテルで食べましょう」
ためらう勇真の手を引っぱって、コンビニへ行く。食材とお酒を買ってラブホテルに入ると、勇真は私をベッドに座らせ、肩を揉んでくれた。私はそっと勇真の手をはずし、勇真のポロシャツに手をかけた。
ええと、勇真はどういうのが好みだったっけ。手が止まってしまうと、妙な間があいた。

「ごめんなさい。先にお風呂を沸かすわ」
「なんであやまるの。ほら、向かい合ってごはん食べようよ」
「セックスじゃなく?」
「彩芽さんがセックスしたいなら、するけど」
器用におにぎりを剥き、私に手渡す。
「私は……」
「彩芽さんは、何がしたいの?いつも、気持ちいい?って聞くけど、彩芽さんはどうしたいの。どうされたいの」
おにぎりを持ったまま、私は無言になった。勇真は、食べ物はおろかお酒をあけようともしない。
私がうつむいていると、
「今日は、ごはん食べたら帰ろう」
勇真がやっと笑って、ビールのプルタブを引いた。私はそれを奪い取り、一気に飲み干す。
「私がしてほしいことを言ったら、してくれるの?何を?みんな私を便利に扱うだけでしょう。私のことなんか見てないくせに」
知っている。男をそういう風にしてしまっているのは、私自身かもしれないってこと。
缶をゴミ箱に投げたら、縁にあたって床を転がった。なんだかみじめで、私は肩で息をしながら泣いていた。唇を噛んで涙を押しとどめて、服を脱ごうとした私を、うしろから勇真が抱きしめた。
「よしよし」
大きな手が背中を撫でる。ちっともいやらしくなく、私を包む。
私の全身の力が、ゆるゆると抜けていく。
埼玉県出身。元少女小説家、小説家。2013年新潮社『R-18文学賞』読者賞受賞。
『主婦病』『幸福なハダカ』『私の裸』新潮社より刊行。他、著書多数。cakesにてエッセイ連載中。
『アラフィフ作家の迷走性活』。