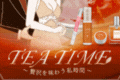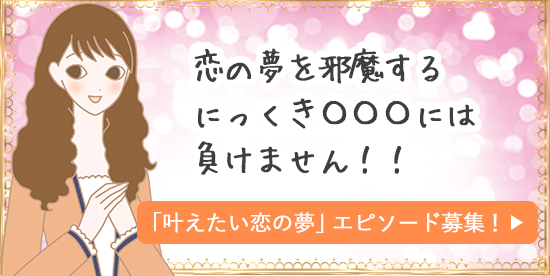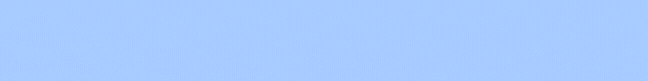沙里ちゃんってまだ乾燥とか感じたことないでしょ。
同僚と連れ立って忘年会の会場へ向かっている時、七つ上の先輩にそう言われた。
当時新卒二年目だった二十四の私は、フェイクファーのロングコートの下にデニムのミニスカートを履き、網タイツの隙間から肌を露出させて暑いのか寒いのかどっちなんだよっていう服装をしていた。
乾燥かあ、確かにどちらかというと自分は脂性肌だけど、洗い物のあと手がかさついたりとかエアコンつけっぱなしにしとくと喉痛くなったりとかはするしな、としばし思いめぐらし、「えーありますよ全然」と答えた。
それからだいたい四年たち、風呂上がりのからだにボディクリームを間髪入れずにすりこんでいる今、あの時の先輩の言葉を思い出していた。
当時の私は、乾燥というものをちっともわかっていなかった。
はっきり覚えている、あれは二十六の秋だった。
二十六の秋から、急にからだが乾くようになった。急にだ。
それまで四肢の乾燥というものを意識せずに生きてきたから、乾きを乾きと認識するのに時間がかかり、原因不明のかゆみ、赤み、痛みに困惑した。
ダニでもいるのかとシーツを替えてみても効果はなく、ためしに持て余していた乳液を四肢に塗ってから寝るようにしたら、かゆみはすっとおさまり、ようやくこれが例の「乾燥」なのだと理解したのだった。
それからというもの、乾燥は私のからだにぴったりと根付いた。
毎晩クリームを塗るくらい大した手間や出費ではないけど、年齢とともに、保湿だのストレッチだの食習慣の改善だの、必要なセルフケアの比重がどんどんどんどん増えていき、終いには身動きが取れなくなってしまうんじゃないだろうかと考えると結構怖い。
とにもかくにもまず保湿、朝晩入念にスキンケアを施さなければいけない。
ぼうっと生きていると私はどんどん乾いていってしまう。
洗面台の前で化粧水を肌に叩き込んでいると、恭介がうしろから忍び寄ってきて「お肌もちもちだねえ」と頬を両手で包まれた。
「ちょっとやめてよ!」
肌が荒れないよう細心の注意を払って暮らしている私にとって、不必要に頬を触るのは最大級のタブーだった。
せめて手は綺麗なんだろうな!?と恭介の直前の行動を推し量る。
こいつ、洗い物のあと毎回ハンドソープで手を洗うタイプの男だっけ?
キッチンのタオルはどの程度清潔だ?
「えー、だってほっぺもちもちで可愛いんだもん」
「顔は本っ当に嫌! 肌荒れの原因!」
「ちょっと触ったくらい大丈夫だよ。過剰じゃない?」
「安易に頬に触るとかマジ全女子が嫌がるから!」
「今までそんなこと言われたことない」
「へー。悪かったね元カノと違って肌荒れしやすい女で!」
ああ、もう少し柔らかい言い方をすればよかった。口に出した瞬間から後悔する。
何で私はこうなんだろう?
十一歳の年の差がある私たちは、決してスキンシップの多いカップルではない。
だからこそ、恭介がからだに触れてくるというのは、今晩セックスをしたいという意思表示に近いのだった。
でも、むやみに頬に触れられるのだけは我慢ならなかった。
朝、自分の顔ににきびを発見する時の気分といったら!
スキンケアの残りの工程を素早くすませ、フォローの気持ちをこめて恭介に甘くすり寄った。
セックスがすごく好きというわけではない。
ただ、セックスがない暮らしというのは考えられない。
乾燥がからだにいつしか根付いていったように、セックスレスも私たちに根付いてしまったらどうしよう。
「ごめん、ちょっと」
いざ挿入という段になって痛みに耐えられず制止すると、恭介は困ったように笑って「今日は無理そうだね。やめとこっか」と頭を撫でた。
その泣きそうな顔が愛おしくて股間が熱っぽくなり、やっぱできるかも、と言おうとしたが、恭介がもう勃っていないのに気づいて言葉を引っ込めた。
セックスをしたかった。
もうどれほどしていないのだろう。
数えるのをやめたが、おそらく数ヶ月はしていない。
とはいえ、まるでないわけじゃないし。
もっと深刻なカップルは山ほどいるだろうし。私たち、仲は良いわけだし。
のろのろと服を着て、軽くキスをして眠りにつく。

学生の頃、学科の助教として勤務していた恭介に心惹かれた。
若さゆえの、不遜とも言えるアプローチの末に交際を始めてからもう八年が経つ。
恭介が勃たないことが増えてから、自分からは誘いづらくなった。
だからこそ、彼がその気の時は確実にセックスを完遂したいのに、恭介が勃起している時に限って今度は自分が濡れなくなってしまったのだった。
あちらを勃てればこちらが濡れず。
……肌も乾くし膣も乾くしサイアクだよ!
……濡れないしレスだし私の二十代は終わった
時刻は真夜中だがそんなの知ったことか。
腹立ち紛れに、亜美と美樹とのグループラインにメッセージを送信すると、翌朝二人から返信が来ていた。
(ミキ)濡れにくいのとセックスレスって女性のお悩み上位二位らしいよ
(ami)沙里、誰も知らねー北欧メタルばっかり聴いてるくせに性の悩みは十人並みなのウケる
……は?北欧メタルはいま普通に流行ってるから
(ミキ)疲れてるんじゃない?リラックスするのも大事かも
(ami)私、冷え性なんだけど、冬とか濡れない時結構あるよー
……そういうもんなんだ
(ami)気になるならローションとか使ってみれば?ラブホに置いてるようなやつ
ホテルなんて、恭介と最後に行ったのはもう何年も前だ。
この状況じゃ、とてもじゃないけど行く気になれないな、と思う。
わざわざホテルに出向いてセックスが未遂に終わったらと思うと恐ろしい。
特に解決はしてないけれど、二人にラインしたことで多少心は軽くなり、ついでに「つか、彼氏でも顔触られんの嫌だよね?」と聞いてみると、ミキからは「彼氏なら嫌じゃない」亜美からは「絶対嫌。セックス中でも嫌。入浴中のみ可」とそれぞれ返事が来た。

秋の訪れとともに誕生日を迎えた。
恭介が予約してくれたレストランのディナーも満足のいくものだったし、二人で選んだおろしたてのパンプスはまだ硬くて指の関節が痛いけど、足元が目に入る度頬がゆるんだ。
十代の頃の、弾けるような感激はなくても、二十八の誕生日は私にじんわりとした幸福感をもたらした。
食事から帰宅すると、宅配ボックスに亜美からの小包が届いていた。
日付指定で、伝票には「化粧品」と書かれている。
「亜美ってばやるじゃん!」と恭介の前でギフトラッピングを施されたリボンをほどくと、美容液のような小瓶が出てきた。
耳慣れないブランド名が記されているので、使用説明書を開くと、どうやら、これはセックスの際に用いる温感タイプのローションであることがわかった。
プライバシーに配慮された梱包が裏目に出た。
あわてて恭介から隠そうとするが、「ねえこれ、エッチなやつなんでしょ」と小瓶をひょいと奪われた。
「違うよ、これは、美容液だよ」
「だって書いてあるよ?女性の敏感な部分にゆっくりなじませるって」
二人のあいだのさっぱりとした涼やかな空気が徐々に熱もって、じっとりと湿っていくのがわかる。
恭介がにじりよってきて、優しく、しかし有無を言わせぬ強さでからだをベッドに倒された。
羞恥と期待で目が潤んでゆく。
シャワーを浴びさせてほしいと必死に訴えても恭介は聞く耳を持たず、私にまたがったまま商品説明をじっくりと読み出した。
どんな情報も読み落とすまいとするような視線の動きは、出会った頃、遠くから目で追っていた恭介の姿を思い起こさせた。
あの頃、二十歳の私は、どうしようもなくこの男が欲しかったのだ。
腰から下の力が抜け、うつぶせに横たわったまま、事後処理をする恭介の背中と、ベッドの下でくしゃくしゃになっているよそ行きのワンピースをぼんやり眺める。
「濡れないこと、悩んでたの?」
恭介に後頭部を優しく撫でられる。
「うん」
「友達に相談してたんだ?」
「うん」
「俺も、その、勃ちが悪いの気にしてて、……病院行ったんだ、この前」
「そうだったの?」
「その時は、心因性の問題だからそのうちできるようになるって言われてそれっきりだったんだけど……俺も友達に相談してみたりサプリ飲んだりしてみようかな」
いや相談するのは相手選んだほうがいいよ!と言うと、恭介はそうだよねと笑った。
「でも、私は恭ちゃんがふにゃチンでも好きだし、大事だよ」
「俺も、沙里ちゃんが濡れなくても肌荒れてても好きだし大事だよ」
八年間一緒にいるのだ。言葉にしなくてもわかっているつもりだった。
それでも、こうして言葉で確認し合うことで、好きとか大事だってことを、私はずっと言葉で言いたかったし、言われたかったのだと思い知った。
でも、また何かの拍子に、ゆっくりと触れ合いが減っていって、好きとか大事って気持ちだけじゃ乗り越えられない夜が訪れるかもしれない。
この八年のうちに、私たちは二人で生きていて、お互いにはお互いしかいなくて、お互いの悩みはお互いにしか当てはまらないと思っていたけど、時々はほかのヒトやモノに助けを求めてもいいのかもしれない。
「あとね、亜美も美樹もほっぺ触られるのは死んでもイヤって言ってたよ」恭介に少し大げさに伝えると、言ったそばから「そうなの?」と両手で頬をぎゅうっと包まれた。
まあどうでもいいや、これから一緒にお風呂に入って顔もきれいに洗うんだし……。
そう思っていたのに、火照ったからだがゆっくりと冷えていくにつれてまぶたが重くなり、べたべたのまま眠ってしまった。
化粧を落とさずに眠り込むなんて、もうずいぶんしていない愚かな行いだった。
翌朝、えくぼの窪みのあたりに大きい吹き出物ができていた。
笑うとちょうど隠れるので、「あばたもえくぼ」と言って大きく笑顔をつくって見せると、恭介はその窪みにキスして、そっと指でつついた。
頬に甘く痛みが残った。

1992年埼玉県生、早稲田大学文化構想学部卒。
第14回「女による女のためのR-18文学賞」読者賞受賞。
『くたばれ地下アイドル』新潮社より発売中