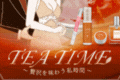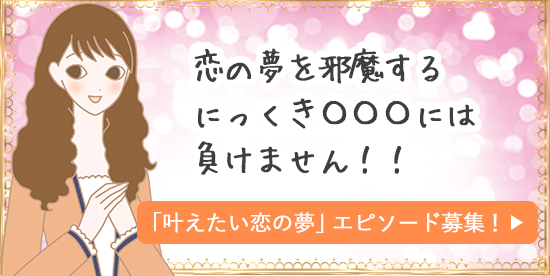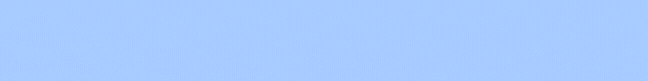鞄の小さい身軽な女に憧れているのに、行きつけのラブホテルに向かう私の荷物は赤子くらい重い。
替えのランジェリーとフルメイクセット、おニューのバイブなどを詰めたリュックに両肩を圧迫され、刻一刻と骨盤が歪んでいっているようで心配になる。
最寄りのコンビニで飲み物を購入し、受付待ちのカップルを尻目にエレベーターに乗り込んであらかじめLINEで伝えられていた部屋に入ると、美樹と沙里はすでに下着姿でベッドに寝転んでいた。
亜美ちん遅刻〜と間延びした声で美樹に咎められる。メンゴメンゴ〜と雑に謝ってリュックからバイブを取り出してベッドにぽんと放り出すと、沙里が何これ新しいやつ?と飛びついた。
黒のベビードールが揺れてへそがあらわになる。
沙里と美樹とは、大学を卒業して間もない時期に合コンで知り合った。
初対面だったのに男そっちのけで超盛り上がり、女三人でラブホ二次会してそのまま朝まで遊んだのだった。
出身大学も違うし共通の趣味があるわけでもないが、それでも何となく気が合って、その後も数ヶ月おきに集まっては初詣をしたり花見に行ったりという関係がゆるやかに続いている。
昔から、その時々で親しくする友人はいても、親友と呼べるような女友達がいない。
いつだって男の子に夢中で、彼氏ができれば恋人の役目も親友の役目もすべて委ねてしまうから、別れのたびに無一文の気持ちになる。
社会人になって新しい友達ができにくくなり、学生時代の友人たちも結婚出産転勤などライフステージが目まぐるしく変わっていく。
子どもが一番の関心ごとである友人とセックスが一番の関心ごとである私とでは、やはりどうしても話が合わなかった。
そんな中で、私にとって美樹と沙里の存在は貴重で気楽だった。
私たちは、親しすぎないからこそあけすけにセックスの話ができた。
会えば楽しくバカ話をするけれども、お互いの歴史を知らないし、パートナーを紹介するような間柄でもない。
照れもしがらみもない独身の三人でセックスについて話し合う時、自分たちだけ時の流れの外にいられるような、なんだかすごく自由な気持ちになれるのだった。
今日のメイントピックはコンドームだ。先日、「私、自分でゴム買ったことない」という美樹の発言にお前ふざけんなよ!と場が紛糾し、沙里と私がそれぞれ自分の推しコンドームをプレゼンすることになったのだった。
「男がラブホのゴム使うのムカつかない?こだわりねーのかよって」と沙里が言う。
「私、男の持参するゴムは信用できないから極力自分の推しコン使ってもらうようにしてる」
ハードケースからコンドームを取り出し、持参したバイブにかぶせる。ほんのりと甘いにおいがただよい、反射的にムラつく。
「でもさーサイズとかあるんでしょ?コンドームって。推しコンもサイズ違いで持っとくの?」
「とりあえずレギュラーサイズ持っとけばだいたいオッケーでしょ」
「どうすんの?俺Lしか入んないんだよね〜って言われたら」
「は?そんなのただのラッキーじゃん!」
「知ってる?コンドームのサイズって長さじゃなくて直径らしいよ」
「ではこれが私の最近の推しコンです。口に入れてもゴムの味しないしいいにおいがします」

チョコレート色のコンドームを装着したバイブを美樹の鼻先につきつけると、「えー私ゴムの上からフェラすんの絶対嫌なんだけど。まずくない?」と顔をのけぞらせた。
「は?口からでも性病ってうつるんだよ」
「フェラでうつるなら諦めもつくよ!まずいのやだもん」
「だからこれはまずくないんだって。舐めていいよ」
美樹は髪を耳にかけ、バイブの裏筋のあたりをぺろりと舐めた。
「えっほんとだまずくない。全然ゴムの味しない!」
「これならゴムの上から舐めたあとでもヨユーでチューできるよ」
「舐めた後のキス嫌がられるとマジムカつくよな」
常日頃から「セックスは温度が命、熱さは感度に直結する」と豪語している沙里は、コンドームも温感ゼリーが付帯しているタイプを愛用しているのだと言い、より膣があたたかく感じる推しコンを私と沙里にひとつずつくれた。
コンドームって、薄さばっかり取り沙汰されるけど、挿入されてる側は薄さってよくわかんないしあったかいとかおいしい方がいいよなあ。
ひとしきり喋って食べて、気まぐれに風呂に入ったりしていればあっという間にチェックアウトの時間が来てしまう。
私たちはホテルを出て、そのまま近くのコンドームショップに足を運んだ。
「うわあものによって値段もけっこー違うんだね。つかさーピル代もバカにならんのになんでゴム代も負担しなきゃなんないの?って思う時ない?」
ずらりと並ぶコンドームを前にして美樹が言う。
「いや別にピルは避妊目的じゃないし」
「私は常に男に対して『抱かせてもらってる』と思ってるからそのくらいの負担は全然」
私と沙里で「ゴム代くらいでガタガタ言うなら転職しろ」「残業しろ」「副業しろ」「彼氏変えろ」と詰めていると、美樹は呆れたように笑って「変えねーよ。つか、結婚すんだよ」と言った。
三人の時が止まった。何を言われたのか、うまく理解できない。
たっぷり五秒間の不自然な沈黙ののち、ようやく「マジで!?あのアプリで知り合った男と!?おめでとう!」と沙里が大きな声を出して美樹の両手を握る。
放心していた私も我に帰り、「おめでとう!」と即座に反応できなかった失態を取り返すように慌てて声を張り上げた。
「プロポーズしちゃいました〜〜〜〜イエーイ」
両手でピースサインをする美樹に、沙里が「そういう重要事項はもっと早く教えてよー!あらかじめわかってたらケーキのひとつも買ってきたのに」と言うと、美樹は「あはは。いーよそーゆうの」と笑う。
まあ、この子はこの先いくらでも祝われる機会があるのだろう。
「プロポーズの言葉は?」
「一生ラブ」
「嘘つくんじゃねえ!」
「本当は?」
「内緒」
「お前っ、自分の性器につけてるニックネームは教えてくれたくせにプロポーズの言葉は恥ずかしいのかよ」
「ねえどんな気分?幸せいっぱい?」
「うーん、なんか、美樹の数奇な人生シーズンワン完。て感じかも」
「完って。結婚はゴールじゃないでしょ」
「いやー、ゴールインとか、ハッピーエンド!的な感慨じゃなくて……。なんていうんだろ。とにかく、うまく言えないけど、特別な何かの終わりを感じるんだよ。年貢の納め時っていうか」
自分でプロポーズしたのに、変かな?と美樹は首をかしげる。
それには答えず、沙里が「シーズンツーもハネるよ、きっと」と言った。
帰りの電車で、美樹が先に降りて行った。
じゃあねーと歩き去る後ろ姿を見送りながら、その服の下に身に着けている、淡いピンクのブラレットとドロワーズのことを思う。
残された沙里と二人、横並びに座席に腰掛け、めでたいねえー。ねー。と言い合う。
三人の時はあんなにかまびすしいのに、二人になると心なしか口数が減る。
そういえば私たちは、お互いに結婚願望があるのかないのか話し合ったことがなかった。
タブー意識があったわけではない。ただほかに話したいことがいくらでもあったのだ。
私たち三人だけは、時の流れの外にいると思っていた。
独身で東京に暮らす二十代の日々は何にも代えがたいものだという共通認識が、三人の胸のうちにあると信じていた。
男の子は大好きだけど、結婚にはまるで興味がない。
友人たちが何人結婚しようが出産しようが、その方針がぶれたことはなかった。
それが今、急にむくむくと心もとなくなり、おそるおそる沙里に尋ねる。
「沙里は結婚とか考えないの?」
沙里は、学生時代に知り合った年上の恋人ともう八年は付き合っているはずだった。
「めちゃくちゃ考えるよ。むしろ、考えすぎてるからこそ結婚してないんだよ私は」
そっかー、とだけ答えて、座席に二センチ深く沈み込む。
座席のくぼみとぬくもりを残して、沙里も電車を降りて行った。
自宅に着いて重たいリュックを放り出し、汗ばんだ服も脱ぎ捨てて下着姿になる。
洗面台でバイブを消毒しながらふと顔をあげると、鏡に映った自分と目が合った。
真っ白なランジェリーをまとった私は掛け値なく綺麗だ。
きっと美樹のドレス姿も、この上なく美しいのだろう。
あの時、私、本当に心からおめでとうって言えたかな?
ちょっとでも意地悪な気持ちになりやしなかったか?
おもしろくなく思わなかったか?
考えていたらいてもたってもいられなくなり、下着姿のまま美樹に電話をかけた。

美樹が出た瞬間、「本当におめでとう生まれてきてくれてありがとう一生幸せでいて!」ってまくしたてたら「時間差で祝うじゃん」と笑われた。
「紹介してね、彼氏さん」
「ヤダよ」
「なんでよ!」
「亜美ちんと沙里とは一生心置きなくセックスの話したいから、絶対紹介しない」
お互いの歴史を知らないしパートナーを紹介するような間柄でもない私たちには、親友という言葉はそぐわないし、「一生」なんて言葉もはっきり言って重い。
それでも、私にとって三人でいる時間は特別で、かったるい日常が軽くなる大切な時間だったのだ。
二人にとってもそうだったらいいんだけどなあ。どうかなあ?
「一生セックスの話すんの?私たち」
「え?するでしょ。しようよ」
美樹が事もなげに言うので、ほんとに私たち一生セックスの話できちゃうかもしんないな、という気持ちになる。
結婚式には呼ばないでいいから、私たちが一番綺麗に見えるランジェリー姿をこれからも見せ合おう。
いくつになってもラブホに集まってバカ話しよう。
たとえいつかセックスに飽きても、またなんか他のおもしろいこと見つけてくるよ。
三人で、誰よりも自由な気持ちでいようね。

1992年埼玉県生、早稲田大学文化構想学部卒。
第14回「女による女のためのR-18文学賞」読者賞受賞。
『くたばれ地下アイドル』新潮社より発売中
・Twitter