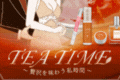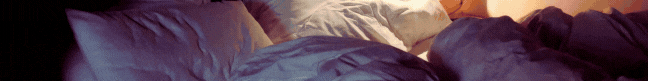佳代子が確かにそう言った。聞き間違いかと思ったが、聞き返してもやはり、佳代子は「えちえちなやつ」と言った。居酒屋を二軒梯子した後だ。佳代子の足取りは、もう立派な酔っ払いのそれだった。
「この近くにねえ、アダルティーなグッズの、専門店があるわけですよ」
駅に向かう人たちの流れから外れると、幾分空気が吸いやすくなる。繋いだ佳代子の手は温かく、アルコール混じりの息は、白く街に溶ける。
「アダルティーなグッズですか」
「そうです、そうなんです。わたくしですね、実はそこの、常連でして。そこでですね、こう、エチエチなやつを、買うのにハマっているんですねえ」
「その、エチエチなやつって、何? コスプレグッズ的な?」
「ううん。バイブ」
バイブ。バイブって、バイブかー。ここまでハッキリ言われるとおもしろいなー。
「ごめん、全然ついていけてないんだけど、そのテンションって、合ってる? 酔ってるから的な?」
「あー、酔ってるけど、全然ふつうに言ってる」
ふつうって言葉を簡単に使うやつって、あんまり信用できないよね、とさっき居酒屋で言っていたばかりではないか。ふつうってなんだ、ふつうって。
「えっと、つまり、大人のおもちゃ的なやつだよね? それを? 買うから、ついてこいってこと?」
「そうそう! サエ、行ったことない? 楽しいよ」
確かに行ったことがない。そういう店に嫌悪感があるわけじゃなくて、ただ単に、機会がなかった。わざわざ調べて足を運ぶほどの好奇心もなかったし、一緒に行こうと誘ってくる人に出会ったこともなかった。付き合った男の中には、そういう道具を使いたがる人もいた。でも大体は使い方が下手で、私はアダルトグッズが体内に入ってくると、道路工事中のアスファルトのように、体がゴリゴリと削られていく感覚だけを味わった。そうしたこともあって、アダルトグッズへの印象があまり良くないのかもしれない。
ピンク、緑、黄色。どぎつい蛍光色が瞳を覆う。よく見れば茶色や灰色のパッケージもある。あらゆる色が店内に敷き詰められている。嗅いだことのない匂いも広がっている。足元は、何がこぼれたのだろうか、ベタベタと貼りついて、不快でしかなかった。佳代子御用達のアダルトグッズ店は、海外製のチューインガムみたいに、甘くてケミカルな印象だった。
*
「佳代子って、どういうの使ってんの?」
上から下までぎっしりと並べられたアダルトグッズを目で追っている佳代子に尋ねる。全くこの世界に明るくない私は、その道の先輩に尋ねるしか店の楽しみ方もわからない。目のやり場に困ろうとしても、全部がエロで固められているから、困りようもなかった。
「んー、中でイくようになってからは、バイブが増えたかな」
今朝の朝食メニューを思い出すように、親友は答える。
「あ、それまでは違ったの?」
「うん、ローターばっかり使ってた。吸うやつ、知ってる? あれ、すごいよ」
「何それ」
「クリに当てんの。もうね、全然違いますから。男に満足できなくなりそうで、こわくて使うのやめましたから」
「こわ、どうなってんのそれ」
いやあ、本当にすごいんですって、あれは。と、また酔っ払いの口調に戻りながら、佳代子は好みのアダルトグッズについて熱く語る。自分から聞いておいて何だが、人が性的快楽について語る様子を見ていると、心がムズムズと痒くなる。店内はいくつかのコーナーに分かれていたが、佳代子の足は迷うことなく、男性器に模した棒が並ぶエリアにたどり着いた。
「すご、こんなに種類あるんだ」
バイブと言っても、太さや長さだけがまちまちなものかと思ったが、よくよく見ると形そのものが人のそれとは少し違っていたり、棒から触手のようなものが生えているものもあった。奥が深い。佳代子はひとつひとつ手にとって、操作性を確かめている。スーパーで野菜を選んでいるようにも見えた。
「サエも、こういうの持ってるー?」
親友はバイブの竿部分を、右手でなぞりながら言った。予期せぬ質問に酔いが一気に覚める。が、頭には熱が灯る。
「あー、いや、持ってない」
「あ、本当―? そうかあ、付き合わせて悪いねえ」
急に申し訳なさそうにされても困る。が、こういう時に押し売りしないところが佳代子のいいところだ。無理に買わされたらどうしようと心配していたけれど、杞憂に終わったみたいだった。
数少ない飲み仲間が、真剣に今夜の相棒(相棒って、きちんと“棒”が入っているんだな、と要らぬ発見をした)を選んでいるところを、冷やかしのように見つめるのもよくないと思い、フロア内をうろついてみる。見たことのない拘束具や、どうやってもうまく着れそうにないコスプレグッズが並ぶ。異世界に来た気分だ、と思った頃には、また元の位置に戻ってきていた。そこで、ふと目に入った一つのバイブに、違和感を覚えた。
――似てる。あの人のものと。

まさか元恋人のペニスを思い出して勝手にエモい気分になっているとは言い出せず、佳代子には黙っていた。が、たぶん、私も酔っていたのだ。佳代子と別れた後、乗るはずだった終電を逃して、私はまたその店に引き返した。そして、元恋人によく似たそれを、自宅に連れ帰ったのである。
*
風呂を沸かして、いつもより丁寧に体を洗う。普段より時間をかけて、毛を剃ってみる。脱衣所には、彼と会うときしかはかなかったショーツと、着心地がつるつると心地よいルームウェアが置いてある。誰に会うわけでもないのに、まるであの人に抱かれる前のように、体をきれいに整える。自慰にここまで準備をすることが、自分でも滑稽に感じた。でも、この時間が何故か、懐かしく、愛おしい。
ベッドランプの明かりだけわずかに残して、寝室の照明を落とす。少しだけ、緊張している。初めて誰かと寝るときみたく、これからどんなことが起こるのだろうと、体の内側が高揚している。毛布に潜ると、枕元に置いておいたバイブを手に取った。長さから、太さから、血管に模したそれまで、どこをとっても彼にそっくりだ。もしかして、ペニスの型を取って、店に売ったのではないか? 一瞬そんな予想をしてみたが、彼がそこまでお金に困っていたり、異常な性癖を持っていたりするとも思えなかった。
まだ付き合っていた頃に彼に教わったとおり、その棒の根元に唇を押し当ててみる。そこから先に向かって、ゆっくりと、舌を這わせる。人の匂いや体温はない。でも、感覚を、体が覚えている。先っぽから歯を立てずに咥えると、舌を使いながら、手を動かした。彼が腰を振っているように思えて、こっちの下半身まで、熱くなる。
自分の唾液が、ベッドランプの光に反射して、元恋人に似たそれは、より人間らしさを増した。片手でショーツまで一息に脱ぐと、それを脚の間に這わせる。陰核まで当てて、信じられないくらいに濡れていたことに気付く。その事実にまた、頭が熱くなる。まだ、入れないで、先端だけ。彼がやっていたように、私の入り口の周りで、ゆっくりと焦らす。自然と腰が動く。もう一度陰核に軽く押し当てて、バイブのスイッチを入れた。その時だった。

(後編へ続く)
Author:カツセマサヒコ
後編がすぐに読みたい方はTwitterをチェック!
\カツセマサヒコ書き下ろし官能小説/
— 夜の保健室出張版 ~寝る前10分の女性の秘めゴト~ (@llove_lc) July 16, 2021
「サエさんさあ、エチエチなやつ買いに行こうよお」
友人の一言で行くことになったグッズ店。
そこで出会った1本のバイブから物語が始まる・・・#カツセマサヒコ #ラブコスメ #からだがおぼえている pic.twitter.com/ntINterijL
マリンビーンズ
ラブコスメで人気となっていた「スカイビーンズ」の先端部分にモーターが付けられたバイブです。これまでよりもGスポットにピンポイントで刺激を与えるデザインで、クリトリスへの快感を逃さない大きめのクリバイブとなっています。本体とクリバイブだけでなく、ヘッド部分にまで搭載されたモーターでの奥への振動を直接感じることができ、一気に3点を刺激することで、大きな快感を得ることができます。